■ 理3・金光教祖御理解・1
今、天地の開ける音を聞いて、目を覚ませ。
■ 理3・金光教祖御理解・2
先の世までも持ってゆかれ、子孫までも残るものは神徳じゃ。神徳は、信心すればだれでも受けることができる。みてる(尽きる)ということがない。
■ 理3・金光教祖御理解・3
天地金乃神と申すことは、天地の間に氏子おっておかげを知らず、神仏の宮寺、氏子の家屋敷、みな神の地所、そのわけ知らず、方角日柄ばかり見て無礼いたし、前々の巡り合わせで難を受けおる。(2)この度、生神金光大神を差し向け、願う氏子におかげを授け、理解申して聞かせ、末々まで繁盛いたすこと、氏子ありての神、神ありての氏子、上下立つようにいたす。
■ 理3・金光教祖御理解・4
此方金光大神あって、天地金乃神のおかげを受けられるようになった。此方金光大神あって、神は世に出たのである。神からも氏子からも両方からの恩人は、此方金光大神である。(2)金光大神の言うことにそむかぬよう、よく守って信心せよ。まさかの折には、天地金乃神と言うにおよばぬ。金光大神、助けてくれと言えば、おかげを授けてやる。
■ 理3・金光教祖御理解・5
これまで、神がものを言うて聞かせることはあるまい。どこへ参っても、方便で願い捨てであろうが。それでも、一心を立てればわが心に神がござるから、おかげになるのじゃ。(2)生きた神を信心せよ。天も地も昔から死んだことなし。此方が祈るところは、天地金乃神と一心なり。
■ 理3・金光教祖御理解・6
目には見えぬが、神の中を分けて通りおるようなものじゃ。畑で肥をかけておろうが、道を歩いておろうが、天地金乃神の広前は世界中である。
■ 理3・金光教祖御理解・7
天地金乃神は昔からある神ぞ。途中からできた神でなし。天地ははやることなし。はやることなければ終わりもなし。天地日月の心になること肝要なり。(2)信心はせんでもおかげはやってある。
■ 理3・金光教祖御理解・8
子供の中にくずの子があれば、それがかわいいのが親の心じゃ。不信心者ほど神はかわいい。信心しておかげを受けてくれよ。
■ 理3・金光教祖御理解・9
天地金乃神は宗旨嫌いをせぬ。信心は心を狭う持ってはならぬ。心を広う持っておれ。世界を広う考えておれ。世界はわが心にあるぞ。
■ 理3・金光教祖御理解・10
神が社へ入っては、この世が闇になる。
■ 理3・金光教祖御理解・11
神は天地の守りじゃから、離れることはできぬぞ。
■ 理3・金光教祖御理解・12
神に会おうと思えば、にわの口を外へ出て見よ。空が神、下が神。
■ 理3・金光教祖御理解・13
神は向こう倍力の徳を授ける。
■ 理3・金光教祖御理解・14
神は荒れ地荒れ屋敷をお嫌いなさる。
■ 理3・金光教祖御理解・15
氏子が真から用いるのは神もひれいじゃが、寄進勧化をして氏子を痛めては、神は喜ばぬぞ。
■ 理3・金光教祖御理解・16
無常の風は時を嫌わぬというが、金光大神の道は、無常の風が時を嫌うぞ。
■ 理3・金光教祖御理解・17
神の綱が切れたというが、神は切らぬ。氏子から切るな。
■ 理3・金光教祖御理解・18
此方のことを、神、神と言うが、此方ばかりではない。ここに参っておる人々がみな、神の氏子じゃ。(2)生神とは、ここに神が生まれるということで、此方がおかげの受けはじめである。みんなもそのとおりにおかげが受けられるぞ。
■ 理3・金光教祖御理解・19
金光大神は形がのうなったら、来てくれと言う所へ行ってやる。
■ 理3・金光教祖御理解・20
此方が天地金乃神よりおかげを受けておることを話にして聞かすのぞ。疑うて聞かぬ者は是非におよばず。かわいいものじゃ。また時を待っておかげを受けるがよし。(2)めいめいに子を持って合点せよ。親の言うことを聞かぬ子が一番つまらぬ。言うことを聞かぬ子は、親もしかたがあるまいが。
■ 理3・金光教祖御理解・21
信心せよ。信心とは、わが心が神に向かうのを信心というのじゃ。神徳の中におっても、氏子に信なければおかげはなし。
(2)カンテラに油いっぱいあっても、芯がなければ火がともらず。火がともらねば夜は闇なり。信心なければ世界が闇なり。
■ 理3・金光教祖御理解・22
天地金乃神といえば、天地一目に見ておるぞ。神は平等におかげを授けるが、受け物が悪ければおかげが漏るぞ。(2)神の徳を十分に受けようと思えば、ままよという心を出さねばおかげは受けられぬ。ままよとは死んでもままよのことぞ。
■ 理3・金光教祖御理解・23
氏子が神と仲ようする信心ぞ。神を恐れるようにすると信心にならぬ。神に近寄るようにせよ。
■ 理3・金光教祖御理解・24
人に誘われて、しょうことなしの信心は、つけ焼き刃の信心じゃ。つけ焼き刃の信心は取れやすいぞ。どうぞ、その身から打ちこんでの真の信心をせよ。
(2)世に勢信心ということを言うが、一人で持ちあがらぬ石でも、大勢かけ声で一度に力をそろえれば持ちあがる。ばらばらでは持ちあがらぬぞ。家内中、勢をそろえた信心をせよ。
■ 理3・金光教祖御理解・25
信心は大きな信心がよい。迷い信心ではいかぬ。一心と定めい。
■ 理3・金光教祖御理解・26
信心に連れはいらぬ。ひとり信心せよ。信心に連れがいれば、死ぬるにも連れがいろうが。みな、逃げておるぞ。(2)日に日に生きるが信心なり。
■ 理3・金光教祖御理解・27
昔から、あの人は正直者じゃ、神仏のような人じゃという者でも、だんだん不幸なことが重なって、世間では、どういうものであろうというようなことがあろうが。(2)なにほど、人に悪いことをせぬ正直者でも、人がよいのと神に信心しておかげを受けるのとは別物ぞ。
■ 理3・金光教祖御理解・28
病人や代々難儀の続く人が神のおかげを受けるのは、井戸がえをするに、八、九分かえて、退屈してやめれば、掃除はできぬ、それで、やはり水は濁っておるようなもので、信心も途中でやめれば病気災難の根は切れぬ。(2)井戸は清水になるまで、病気災難は根の切れるまで、一心に、まめで繁盛するよう元気な心で信心せよ。
■ 理3・金光教祖御理解・29
桜の花の信心より、梅の花の信心をせよ。桜の花は早う散る。梅の花は苦労しておるから長う散らぬ。
■ 理3・金光教祖御理解・30
神を信ずる者は多いが、神に信ぜられる者が少ない。
■ 理3・金光教祖御理解・31
信心する者は、気の切り株に腰をおろして休んでも、立つ時には礼を言う心持ちになれよ。
■ 理3・金光教祖御理解・32
女が菜園に出て菜を抜く時に、地を拝んで抜くというような心になれば、おかげがある。(2)また、それを煮て食べる時、神様いただきますというような心あらば、あたることなし。
■ 理3・金光教祖御理解・33
お供え物とおかげは、つきものではないぞ。
■ 理3・金光教祖御理解・34
ここへ参っても、神の言うとおりにする者は少ない。みな、帰ってから自分のよいようにするので、おかげはなし。神の言うことは道に落としてしまい、わが勝手にして、神を恨むような者がある。(2)神の一言は千両の金にもかえられぬ。ありがたく受けて帰れば、みやげは舟にも車にも積めぬほどの神徳がある。心の内を改めることが第一なり。(3)神に一心とは迷いのないことぞ。
■ 理3・金光教祖御理解・35
信心は日々の改まりが第一じゃ。毎日、元日の心で暮らし、日が暮れたら大晦日と思い、夜が明けたら元日と思うて、日々うれしゅう暮らせば、家内に不和はない。
■ 理3・金光教祖御理解・36
日本国中のあらゆる神を、みな信心すると言うが、それはあまりの信心じゃ。(2)人に物を頼むにも、一人に任すと、その人が力を入れて世話をしてくれるが、多くの人に頼めば、相談に暮れて物事はかどらず。大工を雇うても、棟梁がなければならぬ。草木でも芯というたら一つじゃ。(3)神信心もこの一心を出すと、すぐおかげが受けられる。
■ 理3・金光教祖御理解・37
生きておる間は修行中じゃ。ちょうど、学者が年をとっても眼鏡をかけて本を読むようなものであろうぞ。
■ 理3・金光教祖御理解・38
垢離を取るというが、体の垢離を取るよりは、心のこりを取って信心せよ。
■ 理3・金光教祖御理解・39
此方の行は水や火の行ではない。家業の業ぞ。
■ 理3・金光教祖御理解・40
重い物を負うておるか担いでおれば苦しいが、そうでないから信心は楽じゃ。家業を勤め勤めするがよい。
■ 理3・金光教祖御理解・41
信心は話を聞くだけが能でない。わが心からも練り出すがよい。
■ 理3・金光教祖御理解・42
これほど信心するのに、どうしてこういうことができるであろうかと思えば、信心はもうとまっておる。これはまだ信心が足らぬのじゃと思い、一心に信心してゆけば、そこからおかげが受けられる。
■ 理3・金光教祖御理解・43
死んだからというて、神のおかげを受けずにはおられまいが。死に際にもお願いせよ。
■ 理3・金光教祖御理解・44
狐狸でさえ、神にまつられることを喜ぶというではないか。人は万物の霊長なれば、死したる後、神にまつられ、神になることを楽しみに信心せよ。
■ 理3・金光教祖御理解・45
世に、三宝様踏むな、三宝様踏むと目がつぶれるというが、三宝様は実るほどかがむ。(2)人間は、身代ができたり、先生と言われるようになると、頭をさげることを忘れる。神信心して身に徳がつくほど、かがんて通れ。
(3)とかく、出るくぎは打たれる。よく、頭を打つというが、天で頭を打つのが一番恐ろしい。天は高いから頭を打つことはあるまいと思おうけれど、大声で叱ったり手を振りあげたりすることはないが、油断をすな。慢心が出ると、おかげを取りはずすぞ。
■ 理3・金光教祖御理解・46
痛いのが治ったのがありがたいのではない。いつもまめながありがたいのぞ。
■ 理3・金光教祖御理解・47
祈れ薬れにすればおかげも早いが、薬れ祈れにするからおかげにならぬ。
■ 理3・金光教祖御理解・48
わが子の病気でも、かわいいかわいいと思うてうろたえるといけぬぞ。言うことを聞かぬ時に、ままよと思うてほっておくような気になって、信心してやれ。おかげが受けられる。
■ 理3・金光教祖御理解・49
信心は相縁機縁。
■ 理3・金光教祖御理解・50
とかく、信心は地を肥やせ。常平生からの信心が肝要じゃ。地が肥えておれば、肥をせんでもひとりでに物ができるようなものぞ。
■ 理3・金光教祖御理解・51
天地の間に住む人間は神の氏子。身の上に痛み病気あっては、家業できがたし。身の上安全を願い、家業出精、五穀成就、牛馬にいたるまで、氏子身の上のこと何なりとも、実意をもって願え。
■ 理3・金光教祖御理解・52
信心する者は驚いてはならぬ。これから後、どのような大きな事ができてきても、少しも驚くことはならぬぞ。
■ 理3・金光教祖御理解・53
信心すれば、目に見えるおかげより目に見えぬおかげが多い。知ったおかげより知らぬおかげが多いぞ。後で考えて、あれもおかげであった、これもおかげであったということがわかるようになる。そうなれば本当の信者じゃ。
■ 理3・金光教祖御理解・54
徳のないうちは心配する。神徳を受ければ心配はない。
■ 理3・金光教祖御理解・55
賃を取ってする仕事は、若い時には頼んでもくれるが、年をとっては頼んでくれぬ。信心は、年が寄るほど位がつくものじゃ。信心をすれば一年一年ありがとうなってくる。
■ 理3・金光教祖御理解・56
日にちさえたてば世間が広うなってゆく。ひそかにして信心はせよ。
■ 理3・金光教祖御理解・57
金の杖をつけば曲がる。竹や木は折れる。神を杖につけば楽じゃ。
■ 理3・金光教祖御理解・58
人が盗人じゃと言うても、乞食じゃと言うても、腹を立ててはならぬ。盗人をしておらねばよし。乞食じゃと言うても、もらいに行かねば乞食ではなし。神がよく見ておる。しっかり信心の帯をせよ。
■ 理3・金光教祖御理解・59
習うたことを忘れて、もどしても、師匠がどれだけ得をしたということはない。覚えておって出世をし、あの人のおかげでこれだけ出世したと言えば、それで師匠も喜ぶ。(2)おかげを落としては、神は喜ばぬ。おかげを受けてくれれば、神も喜び、金光大神も喜び、氏子も喜びじゃ。
■ 理3・金光教祖御理解・60
おかげは受け徳、受け勝ち。
■ 理3・金光教祖御理解・61
神より金光大神に、いつまでも尽きぬおかげを話にしておくのぞ。(2)信心しておかげを受けたら、神心となりて人に丁寧に話をしてゆくのが、真の道をふんでゆくのぞ。金光大神が教えたことを違わぬように人に伝えて真の信心をさせるのが、神へのお礼ぞ。(3)これが神になるのぞ。神になりても、神より上になるとは思うな。
■ 理3・金光教祖御理解・62
昔から、人もよかれわれもよかれ、人よりわれがなおよかれというておるが、神信心をしても、わが身の上のおかげを受けて、後に人を助けてやれ。(2)神信心も手習いも同じこと、一段一段進んでゆくのじゃ。にわかに先生にはなれぬぞ。
■ 理3・金光教祖御理解・63
一粒万倍といおうが。一人がおかげを受けたので千人も万人もおかげを受けるようになるから、よい手本になるような信心をせよ。
■ 理3・金光教祖御理解・64
此方は参ってたずねる所がなかった。氏子はおかげを受けて遠路のところを参って来るが、信心して徳を受けて、身しのぎをするようになれ。
■ 理3・金光教祖御理解・65
日柄方位は見るにおよばぬ。普請作事は、使い勝手のよいのが、よい家相じゃ。よい日柄というは、空に雲のない、ほんぞらぬくい、自分に都合のよい日が、よい日柄じゃ。いかに暦を見て天赦日じゃと言うても、雨風が強うては、今日は不祥のお天気じゃと言うではないか。日のお照らしなさる日に良い悪いはないと思え。
■ 理3・金光教祖御理解・66
人間は勝手なものである。いかなる知者も徳者も、生まれる時には日柄も何も言わずに出てきておりながら、途中ばかり日柄が良いの悪いのと言うて、死ぬる時には日柄も何も言わずに駆けっていぬる。
■ 理3・金光教祖御理解・67
何事もくぎづけではない。信心をめいめいにしておらねば長う続かぬ。
■ 理3・金光教祖御理解・68
神参りをするにね雨が降るから風が吹くからえらいと思うてはならぬ。その辛抱こそ、身に徳を受ける修行じゃ。(2)いかにありがたそうに心経やお祓をあげても、心に真がなければ神にうそを言うも同然じゃ。拍手も、無理に大きな音をさせるにはおよばぬ。小さい音でも神には聞こえる。拝むにも、大声をしたり節をつけたりせんでも、人にものを言うとおりに拝め。
■ 理3・金光教祖御理解・69
信心はみやすいものじゃが、みな氏子からむつかしゅうする。三年五年の信心では、まだ迷いやすい。十年の信心が続いたら、われながら喜んで、わが心をまつれ。(2)日は年月のはじめじゃによって、その日その日のおかげを受けてゆけば立ち行こうが。みやすう信心をするがよいぞ。
■ 理3・金光教祖御理解・70
人間は万物の霊長であるから、万物を見て道理に合う信心をせねばならぬ。
■ 理3・金光教祖御理解・71
ここへは信心のけいこをしに来るのである。よくけいこをして帰れ。(2)夜夜中、どういうことがないとも限らぬ。おかげはわがうちで受けよ。子供がある者や日傭取りは出て来るわけにはゆかぬ。病人があったりすれば、捨てておいて参って来ることはできぬ。(3)まめな時ここへ参って信心のけいこをしておけ。
■ 理3・金光教祖御理解・72
人間を軽う見な。軽う見たらおかげはなし。
■ 理3・金光教祖御理解・73
変人になれ。変人にならぬと信心はできぬ。変人というは、直いことぞ。
■ 理3・金光教祖御理解・74
かわいいと思う心が神心じゃ。
■ 理3・金光教祖御理解・75
人を殺すというが、心で殺すのが重い罪じゃ。それが神の機感にかなわぬ。目に見えて殺すのは、お上があってそれぞれのお仕置きにあうが、心で殺すのは神が見ておるぞ。
■ 理3・金光教祖御理解・76
人間は人を助けることができるのはありがたいことではないか。(2)牛馬はわが子が水に落ちていても助けることができぬ。人間が見ると助けてやる。(3)人間は病気災難の時、神に助けてもらうのであるから、人の難儀を助けるのがありがたいと心得て信心せよ。
■ 理3・金光教祖御理解・77
人の悪いことを、よう言う者がある。そこにもしおったら、なるたけ逃げよ。陰で人を助けよ。
■ 理3・金光教祖御理解・78
神の機感にかのうた氏子が少ない。身代と人間と達者とがそろうて三代続いたら家柄人筋となって、これが神の機感にかのうたのじゃ。(2)神の機感にかなわぬと、身代もあり、力もあるが、まめにない。まめで賢うても身代をみたす(尽くす)ことがあり、また大切な者が死んで、身代を残して子孫をきらしてしまう。神のおかげを知らぬから、互い違いになってくる。(3)信心して神の大恩を知れば、無事達者で子孫も続き身代もでき、一年まさり代まさりのおかげを受けることができるぞ。
■ 理3・金光教祖御理解・79
商売をするなら、買い場、売り場というて、もとをしこむ所と売り先とを大事にせよ。人が口銭を十銭かけるものなら八銭かけよ。目先は二銭損のようでも、安うすれば数が売れるから、やはりその方が得じゃ。(2)体はちびるものでないから働くがよい。
■ 理3・金光教祖御理解・80
年寄りを大切にせよ。人間は自分の考えで先へ生まれてきたのではない。みな、神のおかげで生まれてきたので、早く生まれた者ほど世のために働きをたくさんしておる道理であるから、年寄りを敬うのぞ。(2)若い者でも役に立つ人はなんとなく人が敬うようになるが、不都合、不行き届きが重なれば、敬うてくれぬようになる。信心する者は、よう心がけておるがよい。
■ 理3・金光教祖御理解・81
氏子、十里の坂を九里半登っても、安心してはならぬぞ。十里を登り切って向こうへおりたら、それで安心じゃ。気を緩めると、すぐに後へもどるぞ。
■ 理3・金光教祖御理解・82
大蔵省は人間の口をみたようなもので、その口に税金が納まらぬ時は、四分板張った戸一枚で寝てはおられぬ。どこの太郎やら次郎やらわからぬようになろうぞ。
■ 理3・金光教祖御理解・83
一年に分限者になるような心になるな。先は長いぞ。一文二文とためたのは、みてる(尽きる)ことはないが、一時に伸ばしたのはみてやすい。(2)神信心をすれば、我慢我欲はできぬぞ。ぬれ手で粟のつかみ取りの気を持つな。人より一年遅れて分限者になる気でおれ。
■ 理3・金光教祖御理解・84
おごりがましいことをすな。ものは、細うても長う続かねば繁盛でないぞ。細い道でも、しだいに踏み広げて通るのは繁盛じゃ。道に草を生やすようなことをすな。
■ 理3・金光教祖御理解・85
女の身の上、月役、妊娠、つわりに、腹痛まず、腹帯をせずして、産前、身軽く、隣知らずの安産。産後、よかり物、団子汁をせず、生まれた子に五香いらず、母の乳をすぐ飲ませ、頭痛、血の道、虫気なし。(2)不浄、毒断ちなし。平日のとおり。
■ 理3・金光教祖御理解・86
女は世界の田地である。世界の田地を肥やしておかねば貴いものができぬ。(2)女は家の家老じゃ。家老がようなければ城がもてぬというが、女がようなければ家がもてぬ。
■ 理3・金光教祖御理解・87
腹は借り物というが、借り物ではない。万代の宝じゃ。懐妊の時は、神の氏子がわが胎内におると思うて大切にせよ。
■ 理3・金光教祖御理解・88
昔から、親が鏡を持たして嫁入りをさせるのは、顔をきれいにするばかりではない。心につらい悲しいと思う時、鏡を立て、悪い顔を人に見せぬようにして家を治めよということである。
■ 理3・金光教祖御理解・89
此方の道は傘一本で開くことができる。
■ 理3・金光教祖御理解・90
上から下へ水を流すのはみやすいが、下から上へ流すのはむつかしい。(2)道を開くというても、匹夫の俗人から開くのじゃから、ものがむつかしゅうて暇がいる。(3)神のおかげで開かせてもらうのぞ。たとえ一時はむつかしいことがあっても、辛抱してゆくうちには徳が受けられる。
■ 理3・金光教祖御理解・91
もとをとって道を開く者は、あられぬ行もするけれども、後々の者は、そういう行をせんでも、みやすうおかげを受けさせる。
■ 理3・金光教祖御理解・92
神は一体じゃによって、此方の広前へ参ったからというて、別に違うところはない。あそこではおかげを受けたけれど、ここではおかげが受けられぬというのは、守り守りの力によって神のひれいが違うのぞ。(2)神の守りをしておれば、諸事に身を慎み、朝寝をしてはならぬ。早く起きると遅く起きるとは、氏子が参詣の早い遅いにかかわるぞ。
■ 理3・金光教祖御理解・93
氏子は神の守りをしておる者を神と心得て参詣する。(2)守りが留守なら、参詣した氏子は、今日はお留守じゃと言おうが。神の前をあけておくことはできぬ。(3)万事に行き届いた信心をせよ。常平生、心にかみしもを着けておれ。
(4)人には上下があるが、神には上下がない。人間はみな同じように神の氏子じゃによって、見下したり汚がったりしてはならぬぞ。
■ 理3・金光教祖御理解・94
信者に不同の扱いをすな。物を余計に持ってくると、それを大切にするようなことではならぬ。信心の篤いのが真の信者じゃ。
■ 理3・金光教祖御理解・95
世には神を売って食う者が多いが、此方は銭金では拝まぬ。神を商法にしてはならぬぞ。
■ 理3・金光教祖御理解・96
世の人があれこれと神のことを口端にかけるのも、神のひれいじゃ。人の口には戸が閉てられぬ。先を知ってはおらぬぞ。(2)いかに世の人が顔にかかるようなことを言うても、腹を立てな。神が顔を洗うてやる。
■ 理3・金光教祖御理解・97
神を拝む者は、拍手して神前に向こうてからは、たとえ槍先で突かれても後ろへ振り向くことはならぬぞ。物音や物声を聞くようでは、神に一心は届かぬ。
■ 理3・金光教祖御理解・98
心は神信心の定規じゃによって、お伺いする時には、とりわけ平気でなければならぬ。落ち着いて静かに願え。
■ 理3・金光教祖御理解・99
無学で人が助けられぬということはない。学問はあっても真がなければ、人は助からぬ。学問が身を食うということがある。学問があっても難儀をしておる者がある。此方は無学でも、みなおかげを受けておる。
■ 理3・金光教祖御理解・100
めでためでたの若松様よ枝も栄える葉も茂るというではないか。金光大神は子孫繁盛家繁盛の道を教えるのじゃ。
金光教教典(昭和52年3月20日 初版発行)
著作兼発行者 金光教本部教庁
岡山県浅口郡金光町大谷270番地




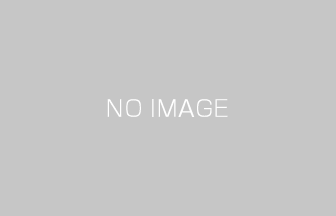









この記事へのコメントはありません。